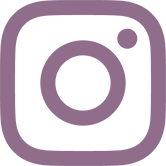村の成り立ち
日本列島は、今から4億年前まではアジア大陸の東の海底にあったといわれています。この海には、フリズナや三葉虫などが生息していました。2億年くらい前になって日本列島は海底から盛り上がり、海底に積もった地層が海上に出てきました。このとき御前山が頭を出し、奥多摩の雲取山、川乗山なども出てきました。御前山の石灰岩には、フリズナや三葉虫の化石が含まれています。(資料館に展示してあります。)
その後、1億年くらいかかけて地下のマグマが地層を押し上げ、三頭山などの山を高くさせたといわれています。三頭山の岩石は、長い間風雨に削られてマグマが冷えて固まった三頭御影といわれる石英閃緑岩です。南秋川沿いにも流れ出した石を見ることができます。
歴史
いまからおよそ、9,000年前もの大昔から人が住んでいた遺跡が村の北谷の奥の、山の上(中之平)で発見され、東京都で一番高いところの遺跡とされています。石器や土器類が発掘され、縄文早期・前期・中期・晩期等のものとされています。他にも村の各所から遺跡が発見されていて、太古より人が住んでいたことが証明されています。
時代は過ぎて、天平の頃(西暦740年代)に宿辺少将橘高安卿という豪族がいて、大岳神社や小岩の八坂神社を造ったといわれています。
応永20年(西暦1413年)頃、檜原城を平山氏が築いたといわれています。天正18年(西暦1590年)、豊臣軍が八王子城を攻め落とし、その年、檜原城も落城してしまいました。その後、徳川氏が江戸城に入り檜原は徳川の天領の地となり、元和9年(西暦1622年)に口留番所ができました。明治1年、府藩県を置くことになり、村は韮山県に属しました。明治11年、武蔵国多摩郡は、西・南・北の三多摩に分かれて、神奈川県西多摩郡檜原村となりました。続いて、明治26年に三多摩が東京府(都)に編入されて現在に至っています。
大正7年、本宿まで電灯がつきました。翌年、中里から小沢まで、大正14年に小岩まで、昭和4年に笹野から上川乗まで、昭和15年に湯久保に、16年に人里、昭和21年に数馬に、昭和34年に藤倉まで、全村に電気が普及しました。
電話は、昭和7年に警察電話が、昭和13年に一般電話(加入者11軒)が、昭和27年に笹野まで、昭和34年共同加入電話が数馬~小岩まで開設、昭和51年にダイヤル電話が全村に入りました。
定期バスは、昭和19年に本宿まで、昭和23年に大沢まで、昭和26年に小沢・上川乗まで、昭和31年に小岩、人里まで、昭和35年に数馬まで、昭和61年に藤倉まで開通して全村にバスが運行するようになりました。
大昔は広葉樹林(ブナ・ミズナラ・シオジ・サワグルミ・トチ)が多く木の実や草の実などもあり、またクマ・イノシシ・シカ・ウサギなどの動物や鳥・魚類も多く食物には困らなかったと思います。当時の人達は、主に山の尾根づたいに行動をしていました。見通しもよく、目的地にもはやく行けますし、災害なども受けにくい利点もあります。

檜原村 名前の由来
平安末期、源氏の武将「平山季重(ひらやますえしげ)の知行地隣、鎌倉幕府の繁栄と共に「柏の庄」と呼ばれ、檜はかしわとも呼ばれるので名づけられたと言われています。
暮らしと仕事
大昔は、狩りや木の実などを集めることが仕事とされていたことでしょう。
山での仕事が中心であり、炭焼の仕事も古くからやっていました。室町時代の記録に、炭を年貢(税金)として納めたとされています。天保年間(西暦1839年)頃、1万6千俵(1俵15kg)もの炭が出荷された記録もあります。炭焼の仕事は、秋から、冬・春までの仕事で朝早くから山に行き、夕方遅くまでの作業で重労働です。火を扱う仕事で、とても熱くて大変です。昭和の始め頃までは、大勢の人達が炭焼きをしていました。第二次世界大戦に日本は敗け、戦後の時代に炭や薪の需要も多くあって大変儲かったときもありました。しかし、昭和30年代、燃料革命によって石油やプロパンガスに変わってしまい、炭を焼く人も減っていきました。
山の仕事には、林業もあります。木の苗を植えたり、下草を刈って木を育てる仕事、雪や風で倒れた木を起こしたり枝を切って育ちを良くしたり、木と木の間を空けて(間伐)やる仕事をします。また、大きくなれば木を伐り出し(伐採)、運搬・製材等の仕事もあります。明暦3年(西暦1657年)に、江戸の大火のときに村からもたくさんの材木が出荷されたとされています。近くは、第二次世界大戦後、戦災により建築材に木材の需要があって、山の仕事は忙しかったそうです。製材工場も村内に12~3軒もありました。それが、外国からの輸入材の影響や建築様式も変わってしまい、材木の需要も少なくなってしまいました。杉の木は、40~50年くらいで柱材等に使えるようになり、檜は60年以上でないと柱材等にはなりません。板材等になるには、杉も檜も100年近く必要です。現在では、国産材が再び注目され、「多摩産材」として檜原村からも材木が出荷されています。
畑は、檜原村は平なところは少なく傾斜地が多く、面積も山間地で広くありません。作物は「ジャガイモ」や「コンニャク」をはじめとして、菜や大根などの蔬菜類など、自家用の野菜を作っている家庭が多いです。一部は観光土産として販売されています。養蚕も、盛んに行われた時代もあったが今はなくなってしまいました。檜原村の多くの住居には養蚕のための建築様式の名残が見られます。
現在の檜原村では、村内で事業を営む人や村外で働く人など多様な暮らし方をしていますが、地域のつながりや伝統芸能は変わらず大切にしています。
観光
昭和のはじめ頃には、山登りの人達がほとんどでした。大岳山や三頭山、御前山等が人気コースでした。昭和30年代頃から観光客も増えてきて、旅館や民宿等も増え、車社会になり一層増えてきて年間120万人もの人達が訪れるようになりました。近年では交通網が発達し日帰り観光が中心となったため廃業する旅館や民宿も目立ちますが、新たにできるカフェや宿泊施設なども見られます。
主な名勝地は払沢の滝、神戸岩、中山の滝、吉祥滝、天狗滝、綾滝等があります。ハイキングコースは、浅間尾根、笹尾根、大岳山、御前山、三頭山等があります。また、数馬にある都民の森は多くの家族連れや登山客で賑わいます。